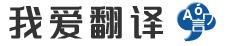- 文本
- 历史
彼に訊きたいことは色々あったのだが、翌朝には結局、彼の言う通りの時刻に
彼に訊きたいことは色々あったのだが、翌朝には結局、彼の言う通りの時刻に馳せ参じた。指定されたのはとあるコンビニエンスストアの駐車場。店の前に彼はいた。黒のボストンバッグとネイビーのダウンジャケットを小脇に抱えている。服装は、綿のシャツにライトグレーのニットを重ね、下はブルーのボトム。私服姿の彼は言ったら悪いがどう見ても学生にしか見えなかった。
降谷くんはすぐにこちらに気付いた。傍に車を停めると、彼は助手席のドアを開けて車内にさっさと乗り込み、後ろの方に抱えていたその荷物を放った。おはようございます、と挨拶が来たのはその後だった。
「……君は、どこへ行くつもりなんだ?」
「首都高に乗りましょう」
俺の質問を無視して降谷くんは淡々と言う。
「僕が案内しますから、赤井は僕の言う通りに運転を」
「だから、どこへ?」
「だから、馬刺しを食べに行くんでしょうが」
昨晩から好きなことばかりを言い連ねているのにも飽き足らず、彼は俺の質問に気分を害した様子でくっきりと眉間に皺を刻んだ。こういう時に折れるのは俺の役目だ。いつのまにかそういう関係が成立してしまっている。
「なぁ、その荷物は何だ?」
俺は質問を変え、後部座席の荷物を一瞥する。彼はそこでやっと笑った。それは微笑んだというのではなく、何か悪戯を仕掛けようとしている子供のような含みのある笑顔だったが、とにかく笑った。
「赤井、明後日も暇ですか?」
だめだ、会話が全く成立しない。俺は諦めてギアを入れ、車を発進させた。
降谷くんはすぐにこちらに気付いた。傍に車を停めると、彼は助手席のドアを開けて車内にさっさと乗り込み、後ろの方に抱えていたその荷物を放った。おはようございます、と挨拶が来たのはその後だった。
「……君は、どこへ行くつもりなんだ?」
「首都高に乗りましょう」
俺の質問を無視して降谷くんは淡々と言う。
「僕が案内しますから、赤井は僕の言う通りに運転を」
「だから、どこへ?」
「だから、馬刺しを食べに行くんでしょうが」
昨晩から好きなことばかりを言い連ねているのにも飽き足らず、彼は俺の質問に気分を害した様子でくっきりと眉間に皺を刻んだ。こういう時に折れるのは俺の役目だ。いつのまにかそういう関係が成立してしまっている。
「なぁ、その荷物は何だ?」
俺は質問を変え、後部座席の荷物を一瞥する。彼はそこでやっと笑った。それは微笑んだというのではなく、何か悪戯を仕掛けようとしている子供のような含みのある笑顔だったが、とにかく笑った。
「赤井、明後日も暇ですか?」
だめだ、会話が全く成立しない。俺は諦めてギアを入れ、車を発進させた。
0/5000
你要问我什么是他有多种,但是第二天早上毕竟是叁级突出的,他说这条街的时间。由于停车场的短语便利店。在店门前他。我们有自己的胳膊下一个黑色的波士顿包和海军羽绒服。衣服,堆着浅灰色针织棉衬衫,下的蓝色底。看什么是坏的,如果他说便衣的外观并没有出现不仅给学生。<br>古谷坤很快就注意到这里。而附近把车停下来,他迅速钻进车里,打开副驾驶座的车门,它已经把行李是有朝后面。早上好,和问候来到当时。<br>“......你是,我打算去哪里?” <br>‘让我们坐大都会,’ <br>古屋坤,无视我的问题漠然说道。<br>“因为我会引导你,阿凯开车到街上指着我说,” <br>“那么,到哪里?” <br>“这么说,但你会去吃马生鱼片” <br>也已被选中说我从昨晚唯一喜欢的不到百无聊赖,他切碎皱纹清脆和眉毛在哪得罪了我的问题的状态。在这样的时刻破发是我的角色。不知不觉样的关系,他们已经建立。<br>“我在想,是什么行李?” <br>我改变的问题,望了一眼后座的行李。他勉强笑了那里。这并不是因为微笑,是包括一定的微笑像一个孩子,你是想引起一些恶作剧,但无论如何,笑了起来。<br>“阿凯,也是一个?工作之余后天白天” <br>没用的,谈话也不满意。我把齿轮放弃,被允许启动汽车。
正在翻译中..
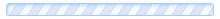
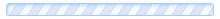
有很多事情我想问他,但第二天早上,他终于在他所说的时间。 指定的是一家便利店的停车场。 在商店前面,他。 他穿着黑色的波士顿包和海军羽绒服。 衣服上堆着浅灰色针织品,底部是蓝色底部。 穿着便衣,他只对学生看,不管他看起来出了什么问题。<br> 伊塔尼昆立刻注意到了这一点。 把车停在一边,他打开乘客座椅的门,迅速上车,把行李放在后面。 早上好,然后是问候。<br>「...... 你要去哪里? 」<br>"让我们骑在首都高。<br> 无视我的问题,阿苏米·库恩说。<br>"我会带你去的,所以阿凯照我说的开车。<br>"那么,你在哪里? 」<br>"所以,我会去吃马刺。<br> 他从昨晚起就一直抱怨自己喜欢什么,他似乎对我的问题感到恼人,在眉毛之间刻了一把条纹。 在这样的时刻,我的职责是打破它。 这种关系在不知不觉中被建立起来。<br>"嘿,你的行李是什么? 」<br> 我改变了问题,瞥了一眼后座的行李。 他终于在那里笑了起来。 这不是微笑,而是一个像孩子一样的微笑,他试图制造一些恶作剧,但无论如何,他都笑了。<br>"阿凯,你后天有空吗? 」<br> 不,谈话根本不存在。 我放弃了,把装备放进去,开始开车。
正在翻译中..
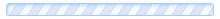
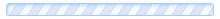
想问他的事情有很多,但第二天早上,还是赶到了他所说的时间。指定的是某个便利店的停车场。他在商店的前面。夹着黑色的波士顿包和海军的羽绒服。服装,棉的衬衫重叠浅灰色的针织衫,下面是蓝色的下身。他穿便服讲得不好,怎么看都像个学生。<br>降谷马上注意到了这里。他把车停在旁边,打开副驾驶座的车门,赶紧进入车内,把抱在后面的行李放了出去。“早上好”的问候是在那之后。<br>“……你打算去哪里?<br>“我们上首都高吧。”<br>无视我的提问的降谷君淡淡的说道。<br>“我来带路,赤井就按照我说的去开车。”<br>“所以,去哪里?”<br>“所以我们去吃生马肉吧。”<br>他从昨晚开始就一个劲儿地说着喜欢的事还不够腻烦,以害我提问的情形清楚地在眉间刻下了皱纹。在这种时候让步是我的任务。不知什么时候那样的关系成立了。<br>“啊,那个行李是什么?”<br>我改变了提问,瞥了一眼后座的行李。他在那里终于笑了。那并不是微笑,而是像是在做恶作剧的孩子般含蓄的笑容,总之笑了。<br>“赤井,后天也有空吗?”<br>不行,对话完全不成立。我放弃了装上齿轮,让车子发动了。<br>
正在翻译中..
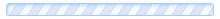
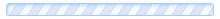
其它语言
本翻译工具支持: 世界语, 丹麦语, 乌克兰语, 乌兹别克语, 乌尔都语, 亚美尼亚语, 伊博语, 俄语, 保加利亚语, 信德语, 修纳语, 僧伽罗语, 克林贡语, 克罗地亚语, 冰岛语, 加利西亚语, 加泰罗尼亚语, 匈牙利语, 南非祖鲁语, 南非科萨语, 卡纳达语, 卢旺达语, 卢森堡语, 印地语, 印尼巽他语, 印尼爪哇语, 印尼语, 古吉拉特语, 吉尔吉斯语, 哈萨克语, 土库曼语, 土耳其语, 塔吉克语, 塞尔维亚语, 塞索托语, 夏威夷语, 奥利亚语, 威尔士语, 孟加拉语, 宿务语, 尼泊尔语, 巴斯克语, 布尔语(南非荷兰语), 希伯来语, 希腊语, 库尔德语, 弗里西语, 德语, 意大利语, 意第绪语, 拉丁语, 拉脱维亚语, 挪威语, 捷克语, 斯洛伐克语, 斯洛文尼亚语, 斯瓦希里语, 旁遮普语, 日语, 普什图语, 格鲁吉亚语, 毛利语, 法语, 波兰语, 波斯尼亚语, 波斯语, 泰卢固语, 泰米尔语, 泰语, 海地克里奥尔语, 爱尔兰语, 爱沙尼亚语, 瑞典语, 白俄罗斯语, 科西嘉语, 立陶宛语, 简体中文, 索马里语, 繁体中文, 约鲁巴语, 维吾尔语, 缅甸语, 罗马尼亚语, 老挝语, 自动识别, 芬兰语, 苏格兰盖尔语, 苗语, 英语, 荷兰语, 菲律宾语, 萨摩亚语, 葡萄牙语, 蒙古语, 西班牙语, 豪萨语, 越南语, 阿塞拜疆语, 阿姆哈拉语, 阿尔巴尼亚语, 阿拉伯语, 鞑靼语, 韩语, 马其顿语, 马尔加什语, 马拉地语, 马拉雅拉姆语, 马来语, 马耳他语, 高棉语, 齐切瓦语, 等语言的翻译.